立風書房
1977年
たまたま図書館から借りてある『現代俳句全集』の第四巻、波多野爽波、藤田湘子、古澤太穂、細見綾子、三橋敏雄、森澄雄の6名が収録された巻から波多野爽波を30句。
爽波は4年前に若くして亡くなった田中裕明の師。代表句に「鳥の巣に鳥が入つてゆくところ」「末黒野に雨の切尖かぎりなし」「冬空や猫塀づたひどこへもゆける」「金魚玉とり落としなば舗道の花」等。
「俳句スポーツ説」「多作多捨」で知られる。出来合いの情趣がまつわりつく前に瞬時に対象を写生する。その速度により、日常の風景から見慣れない位相があらわれる。
この世界は、自然も事物も人に関心など持っていない。悪意すらない。ただただ明快で意味がなく、非情ですらない。それを非情と感じるのは人の側の都合で、人と外界との接触面に薄いガラスのように立ち現われる、隠喩や象徴といった重苦しい世界解釈から高速で離れる句たちのひんやりとした質感が、廃墟のように心地よい。
滝見えて滝見る人も見えてきし
螢とぶ下には硬き舗道かな
遠足の列伸ぶところ走りをり
俳諧味・滑稽の句にも見えかねないが、滑稽は通常の世界観を認めた上でそれをずらしたときに発生する。爽波の興味がそうしたところにあるとも思えず、単なる粗密の度合いのばらつきと運動とに還元されてしまったものとしての人の列が主眼なのではないか。かといってその力学的ともいえる視線が自然科学的体系性にめでたくおさまり、晴れやかさをもたらすわけでもない。既成の世界観におさまってしまうものはどの道大した句ではない。
秋草の中や見事に甕割れて
桜貝長き翼の海の星
隙間風さまざまのもの経て来たり
凍鶴を見てきぬ皿に肉赤き
ドレスの背につきまとふ蚊よ遠い月
柏餅の太い葉脈メス煮られ
猫走り去りてしぐるる捨椀あり
青柿の夜々太りつつ星は気儘
この辺、二つのものの取り合わせの句が続く。概ね緊張をはらみ不穏である。
矢の如く速達がきて石榴の家
菜蟲とる顔色悪き男出て
鳥渡る理髪休みに白布引き
空港出て田植汚れの電柱立つ
秋の蛇ネクタイピンは珠を嵌め
弟子の田中裕明に「穴惑ばらの刺繍を身につけて」という不思議な句がある。「穴惑」は秋の季語で、冬眠場所が定まらずにうろうろしている蛇を指す。発想の出どころがよくわからなかったが、今回爽波の句を拾いなおしてこれが元であったのかもしれないと思い至った。
茸番の声を発する続けざま
こういう不気味な句がよくぞ出てくるものだと思う。
茸番が木偶のように茸に動かされ、茸の意思を代行して得体の知れぬ音声を発しているようにも見える。
鯉泳ぐ底も白砂や堂雪解
ちぎり捨てあり山吹の花と葉と
帚木のつぶさに枝の岐れをり
帚木が帚木を押し傾けて
この辺の3句、自然をそのまま描きながら共感や解釈を許さない絶対的な強度を得ているというべきか。
掛稲のすぐそこにある湯呑かな
焼藷をひそと食べをり嵐山
六月の藪の大きく割れゐたる
じやがいもの花の三角四角かな
掃きながら木槿に人のかくれけり
前掲の「鳥渡る理髪休みに白布引き」といい、この句といい、人の営為やその痕跡を描きながらも無人くささが漂う。
ハンマースホイの、現前がそのままで不在をあらわすような絵に通じるところもある。ただし人界の残像が、無としての神の記憶のなかに残るとしたらかくもあろうかという、ハンマースホイの時間の経過感をともなううっすらとした湿り気は共有しない。悲痛や喪失の情がまつわりつかないからで、線が明瞭で、その分呵責がない。
伐りし竹ねかせてありて少し坂
蟷螂の半死半生流れけり
蓑虫にうすうす目鼻ありにけり
あかあかと屏風の裾の忘れもの
波多野爽波(はたの そうは)
大正12年(1923)~平成3年(1991)68歳没。東京都生れ。「青」主宰。
虚子に師事。「ホトトギス」同人。「青」創刊主宰。関西の前衛派と交じわりつつ独自の道を歩んだ。京都大学出身。(「俳人名鑑」より)
« 2008年3 月 | メイン | 2008年12 月 »





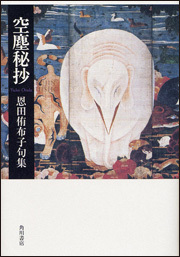

最近のコメント