 岩波書店
岩波書店
1990年
ブログに上げるもの以外にも日々大量の俳句を読む。読むだけではなく、自分でも作らなければならない。
今出来の句ばかり見ていてやや飽きたので、漱石の句集を借りてきた。
天平仏のようなアルカイック(古拙)な面持ちで物欲しげなところがなく、淡々たるところがときにそのまま不気味さを閃かせることもある。
雀来て障子にうごく花の影
仮位牌(かりいはい)焚く線香に黒むまで
兄の妻・登世(享年25歳)を悼む連作のうちの1句。
仮位牌は漆塗りのではなく白木のものか。本式のに換えるまでのわずかな間に焚かれる線香の多さが悲しみの深さを暗示する。
弦音(つるおと)にほたりと落る椿かな
明治27年の句。註によると、この年の菊池謙二郎宛ての私信に「大弓大流行にて小生も過日より加盟致候」とあるらしい。
柳散る紺屋(こうや)の門の小川かな
秋の山南を向いて寺二つ
無欲・無技巧の上に、「ものそのものを投げ出した」といった表現的な力みも何もない素朴そのものの味わい。
関係ないが中里介山『大菩薩峠』の中に作中人物のひとりが「~南面す」という座五の素人俳諧をものしてたしなめられる場面があった気がする。君子(のすまい)は南面すべしという思想があり、平安京などもそれに則って設計されている。「南面」は皇帝・天皇がすることであって庶民が使う言葉ではないということだった。
吹き上げて塔より上の落葉かな
蜻蛉や杭を離るる事二寸
この辺の自然詠、非意味に徹した爽波のニヒリズムとも違うし、個我の悟達の内に自然を属領化してしまう虚子とも違う。木や石が眺めている風景のようにも見える。
冬籠米搗(つ)く音の幽(かす)かなり
親展の状燃え上がる火鉢哉
黙然と火鉢の灰をならしけり
梁山泊(りょうざんぱく)毛脛(けずね)の多き榾火哉
直前の「榾の火や昨日碓井を越え申した」に並び榾(たき物にする木切れ)の句が二つ。
梁山泊はいうまでもなく『水滸伝』で108人の無頼漢が集まった沼沢地、榾の髭根の多さを伝奇小説の無頼漢に見立てた。滑稽と実感の両立した句。
叩かれて昼の蚊を吐く木魚かな
うかうかと我門過る月夜かな
月に見とれて自分の家を通りすごしてしまった。江戸俳諧の風味もまだ残る。
花に暮れて由(よし)ある人にはぐれけり
永き日や韋駄(いだ)を講ずる博士あり
註によると井上哲次郎のこと。「韋駄」はヴェーダでインド最古の宗教文献とある。明治以外では成り立たない風情の句ではないか。「裸体なる先生胡坐(こざ)す水泳所」などというのもあり、この「先生」も明治の匂い。
どこやらで我名よぶなり春の山
市中(まちなか)に君に飼はれて鳴く蛙
月東(つきひがし)君は今頃寐てゐるか
餅を切る庖丁鈍し古暦(ふるごよみ)
ふるひ寄せて白魚崩れんばかりなり
夜相撲やかんてらの灯(ひ)をふきつける
能もなき渋柿どもや門の内
遠く見る枯野の中の烟かな
炭を積む馬の脊に降る雪まだら
われ折々死なんと思ふ朧かな
次に「春この頃化石せんとの願あり」が並んでいる。木か石が見ているようなと先に書いたが、漱石の死のイメージは気化と石化で、人の姿のままあの世にといったものではなかったようだ。
栗を焼く伊太利人(イタリーじん)や道の傍(はた)
衣更(きぬかえ)て見たが家から出て見たが
恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩(や)せにけり
骨の上に春滴(したた)るや粥の味
あるほどの菊抛げ入れよ棺(かん)の中
なお今回借りてきたのは『漱石俳句集 漱石文学作品集16』という版だったが、これはもともと岩波文庫で出ていたのをそのまま収録したものらしい。
« 2008年12 月 | メイン | 2009年2 月 »




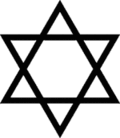
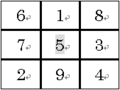



最近のコメント